こんにちは。今日は7月1日です。
7月1日といえば「弁理士の日」であります。そんなこと弁理士しか知らん気もしますが。
「弁理士の日について」
https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/history/the-date-of-the-patent-attorneys/
そして7月1日は、わたくし ひろたが、この「ip-hands経営サポート」を開業して1周年でございます。誰も祝ってくれないので、自分でひっそり祝います。やーっ

「弁理士の日」ブログ企画
さらに、7月1日は、毎年恒例の「弁理士の日」ブログ企画の投稿日です。ドクガクくん、毎年企画ありがとう。
今年のお題は「生成AIと知財業界」です。
生成AI、あまりに日進月歩すぎて怖いですね。
便利すぎてもはやAI無しで業務を行うことは考えられんです。
現在、ひろたは、弁理士業8割+中小企業診断士業2割 という感じでやってますが、どちらの業務でもAI大活躍です。
どちらの士業も「AIに淘汰される」かどうかの議論がありますが、もう耳ダコですので、ここで議論する気はないですが、淘汰される業務が一部あるのは事実ですよね。
これは、わたしが年寄りになったから実感することなんですが、この歳になった段階でAIが登場したのは、とてもありがたく思ってます。例えば、根気のいる作業とか細かくて集中力がいる作業とか、若かりし頃はわりと平気でできましたが、だいぶ辛くなってきました。
弁理士業務の中でのこういう作業は、専門知識が必要なことが前提なので、誰でもそつなくやってくれるわけではないですが、AIさんは適切な指示を与えればそつなくやってくれる(ことが多い)。しかも無限に(笑)。とってもありがたいです。
しかし、いままで、こういった作業に ”面倒で時間がかかるから” という理由でフィーを取ってる部分もあったので、そういう意味では「AIに淘汰される」ことになるんでしょうね…。
今後は、ますます、AIが容易に解を出せない領域 – もっと上流側の領域 – でお客様サポートをして、それでお客様に喜んでいただきフィーを取れるような専門性が必要になるんでしょうね。
めちゃありきたりなこと言ってすみません。
弁理士業に限らず、あらゆる士業さん、ひいては、あらゆるホワイトカラーの仕事で同じような状況だと思います。
主に商標・意匠・不競法に関連する業務
前置き長くなってしまいましたが、いま現在、わたしが弁理士業の中のどのような場面でどのようにAIツールを使っているか、まとめてみます。ただし、わたしは普段、商標・意匠・不競法に関連する業務に携わっているので、その業務範囲限定です。
ちなみに、商標や不競法は、基本的に公開情報を扱うので、特にAIと相性がよいと感じています。
自分はそれほどAIに詳しいわけでなく、おそらく皆さんと同じような使い方で目新しさはないと思いますが、ざっと、こんな感じで使っています(もっと良いツールがあるかもしれないが、単純に知らないです。ご存知だったら教えてください)。
【調べもの】
・ツール: Gemini, Perplexity, GensPark等のDeep Research系
・目的:識別性や周知性等の市場調査、不使用調査 など。
【アイデア出し・企画】
・ツール:Gemini、GhatGPT
【作業効率化】
○元データありの情報整理
・ツール:NotebookLM、ChatGPT
・目的:判例要約、指定商品役務の抽出(例えばウェブサイトから)、指定商品役務と類似群コードの紐づけ など。
○プレゼン資料作成(【アイデア出し・企画】 のあと)
・ツール:GensPark
・目的:いい感じのパワポたたき台作り
○商品構成文章作成
・ツール:GhatGPT
・写真等をもとに製品の構成を特許クレーム風に書いてもらう(係争系で使います)
うん。結構使ってるね。てへ。
とはいえ、AIを使ってるヒトならわかると思いますが、(単純作業系以外)ハレーションが100%なかったことは、ほとんど無いです。特に調べものについては、シュッとした優等生のたたずまいで、しれっと嘘を紛れ込ませてくるので、めちゃんこ要注意です。見た目に騙されず、必ず元データチェックをしないと怖いです。泥臭いですが。
自分ルール
もはやすぐAIに頼っちゃう癖がついちゃいましたが、自分の中では「これにはAIを使わない」という明確なルールがあります。それは以下の2つの観点からです。
(1)創造性リスペクトの観点から
・クリエーターさんの創造性を軽視するような結果が出てくる指示は出さない。
・特に、画像や動画は、基本的に生成させない(生成できちゃったとしても、ありふれたアイコン等以外は、特定のクリエーターさんがオリジナルで創作したと明確にわかるものに置き換える)
(2)機密性の観点から
・弁理士には高度な守秘義務が課せられていることに鑑み、安全サイドに立って、「弁理士業務 AI 利活用ガイドライン」に従う。端的には、例えば、ChatGPTでは、非学習モードでも、データ自体は海外サーバーに保管されることになるので、お客様からOKの明示がない限りは、秘密情報は入れない。
(2)は弁理士的には当たり前のルールですが、肝に銘じるつもりで。
最後に
ちなみに、今日のブログは、AIに書かせたものではありません(笑)。
なので時間がそこそこかかって、7月1日の日付変わるギリギリ時間の投稿になってまったよ!


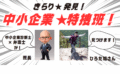
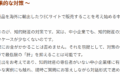
コメント